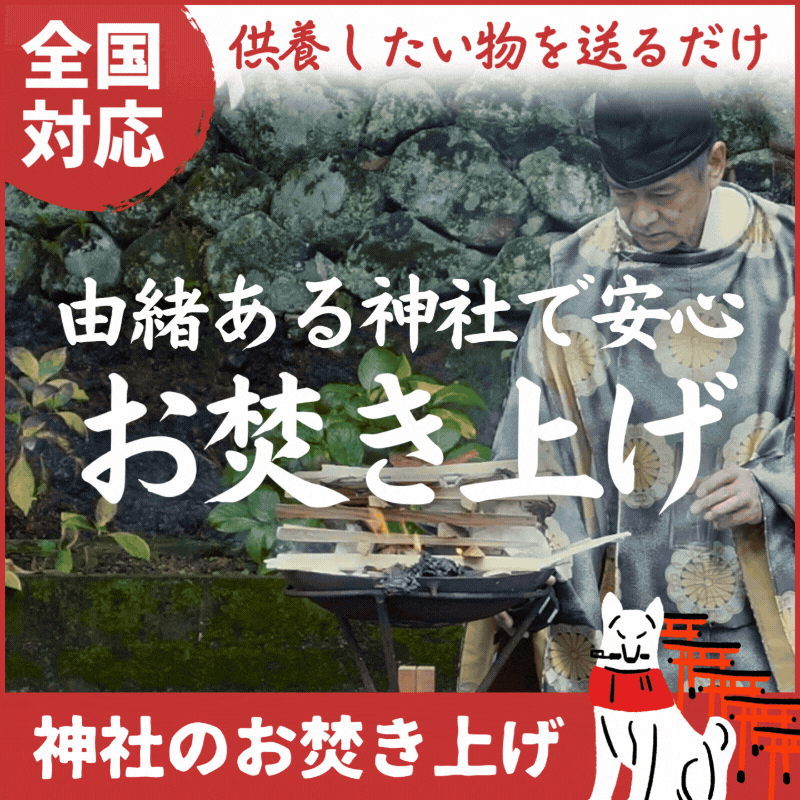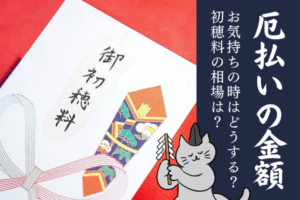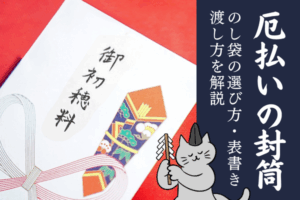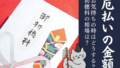2026年(令和8)は、2002年(平成14)、1985年(昭和60)、1966年(昭和41)生まれの男性と、2008年(平成20)、1994年(平成6)、1990年(平成2)、1966年(昭和41)生まれの女性が本厄にあたります。
1985年(昭和60)生まれの男性と、1994年(平成6)生まれの女性が大厄です。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
2026年の厄年早見表(男女)
| 男性 | 前厄 | 24歳 | 41歳 | 60歳 | |
| 2003年(H15)生 ひつじ |
1986年(S61)生 とら |
1967年(S42)生 ひつじ |
|||
| 本厄 | 25歳 | 42歳★大厄 | 61歳 | ||
| 2002年(H14)生 うま |
1985年(S60)生 うし |
1966年(S41)生 うま |
|||
| 後厄 | 26歳 | 43歳 | 62歳 | ||
| 2001年(H13)生 へび |
1984年(S59)生 ねずみ |
1965年(S40)生 へび |
|||
| 女性 | 前厄 | 18歳 | 32歳 | 36歳 | 60歳 |
| 2009年(H21)生 うし |
1995年(H7)生 いのしし |
1991年(H3)生 ひつじ |
1967年(S42)生 ひつじ |
||
| 本厄 | 19歳 | 33歳★大厄 | 37歳 | 61歳 | |
| 2008年(H20)生 ねずみ |
1994年(H6)生 いぬ |
1990年(H2)生 うま |
1966年(S41)生 うま |
||
| 後厄 | 20歳 | 34歳 | 38歳 | 62歳 | |
| 2007年(H19)生 いのしし |
1993年(H5)生 とり |
1989年(S64/H1)生 へび |
1965年(S40)生 へび |
厄年は「数え年」の年齢で確認しましょう
厄年は、日本の古い年齢の数え方である「数え年」を基準に数えます。
数え年の場合、12月1日に生まれた子どもは、生まれた時点で1歳、生後1カ月の元日で2歳になります。
満年齢とは1、2歳の差が生じるため、厄年を確認する際は「生まれ年」で確認するのがおすすめです。
2026年 女性の厄年(数え年)
| 前厄 | 18歳 | 32歳 | 36歳 | 60歳 |
| 2009年(H21)生 うし |
1995年(H7)生 いのしし |
1991年(H3)生 ひつじ |
1967年(S42)生 ひつじ |
|
| 本厄 | 19歳 | 33歳 ★大厄 | 37歳 | 61歳 |
| 2008年(H20)生 ねずみ |
1994年(H6)生 いぬ |
1990年(H2)生 うま |
1966年(S41)生 うま |
|
| 後厄 | 20歳 | 34歳 | 38歳 | 62歳 |
| 2007年(H19)生 いのしし |
1993年(H5)生 とり |
1989年(S64)生 へび |
1965年(S40)生 へび |
女性の厄年は19歳、33歳、37歳、61歳が本厄、その前後に前厄・後厄があります。
数え33歳(1994年、平成6年生まれ)の方は今年が「大厄」なので、特に慎重な行動を心がけましょう。
2026年 男性の厄年(数え年)
| 前厄 | 24歳 | 41歳 | 60歳 |
| 2003年(H15)生 ひつじ |
1986年(S61)生 とら |
1967年(S42)生 ひつじ |
|
| 本厄 | 25歳 | 42歳 ★大厄 | 61歳 |
| 2002年(H14)生 うま |
1985年(S60)生 うし |
1966年(S41)生 うま |
|
| 後厄 | 26歳 | 43歳 | 62歳 |
| 2000年(H12)生 たつ |
1984年(S59)生 ねずみ |
1965年(S40)生 へび |
女性の厄年は25歳、42歳、61歳が本厄、その前後に前厄・後厄があります。
数え42歳(1985年 昭和560年生まれ)の方は今年が「大厄」なので、特に慎重な行動を心がけましょう。
2027 令和9年の厄年は?
| 男性 | 前厄 | 24歳 | 41歳 | 60歳 | |
| 2004年(H16)生 さる |
1987年(S62)生 うさぎ |
1968年(S43)生 さる |
|||
| 本厄 | 25歳 | 42歳★大厄 | 61歳 | ||
| 2003年(H15)生 ひつじ |
1986年(S61)生 とら |
1967年(S42)生 ひつじ |
|||
| 後厄 | 26歳 | 43歳 | 62歳 | ||
| 2002年(H14)生 うま |
1985年(S60)生 うし |
1966年(S41)生 うま |
|||
| 女性 | 前厄 | 18歳 | 32歳 | 36歳 | 60歳 |
| 2010年(H22)生 とら |
1996年(H8)生 ねずみ |
1992年(H4)生 さる |
1968年(S43)生 さる |
||
| 本厄 | 19歳 | 33歳★大厄 | 37歳 | 61歳 | |
| 2009年(H21)生 うし |
1995年(H7)生 いのしし |
1991年(H3)生 ひつじ |
1967年(S42)生 ひつじ |
||
| 後厄 | 20歳 | 34歳 | 38歳 | 62歳 | |
| 2008年(H20)生 ねずみ |
1994年(H6)生 いぬ |
1990年(H2)生 うま |
1966年(S41)生 うま |
2027年(令和9)は、2003年(H15)、1986年(S61)、1967年(S42)生まれの男性と、2009年(H21)、1995年(H7)、1991年(H3)、1967年(S42)生まれの女性が本厄にあたります。
1986年(S61)生まれの男性と、1995年(H7)生まれの女性が大厄です。
厄払い(厄除け)祈願のおすすめ神社・お寺【都道府県別】
厄払い(厄除け)祈願で有名な神社・お寺を都道府県ごとにまとめています。
↓お住まいの都道府県をクリックしてください
| 北海道・東北 の厄払い祈願 |
宮城県 |
| 山形県 | |
| 東京・関東 の厄払い祈願 |
茨城県 |
| 栃木県 | |
| 群馬県 | |
| 埼玉県 | |
| 千葉県 | |
| 東京都 | |
| 神奈川県 | |
| 山梨県 | |
| 長野県 | |
| 北陸 の厄払い祈願 |
新潟県 |
| 中部 の厄払い祈願 |
岐阜県 |
| 静岡県 | |
| 愛知県 | |
| 近畿 の厄払い祈願 |
滋賀県 |
| 京都府 | |
| 大阪府 | |
| 兵庫県 | |
| 奈良県 | |
| 和歌山県 | |
| 中国 の厄払い祈願 |
岡山県 |
| 広島県 | |
| 四国 の厄払い祈願 |
徳島県 |
| 愛媛県 | |
| 九州・沖縄 の厄払い祈願 |
福岡県 |
| 熊本県 | |
| 大分県 | |
| 鹿児島県 | |
| 沖縄県 |
厄払い(厄除け)祈願はいつ受けるべき?

厄払い(厄除け)祈願を行う時期に明確な決まりはなく、ご自身の好きなタイミングで参拝祈願して問題ありません。
厄年にあたる年の初めに祈願するのが一般的で、1月1日の元旦から節分(2月3日)にかけて、厄払い祈願の参拝者で多く賑わいます。
全国の神社・お寺では通年で厄払い祈願を受け付けているので、年始に限らず、ご自身の誕生日や、何か不幸や心配事があった際には祈願を受けると良いでしょう。
厄払い(厄除け)祈願は神社とお寺どちらで受けるべき?

厄払い(厄除け)祈願は神社とお寺どちらでも受けることができますが、儀式の内容と意味合いが異なります。
「厄払い」は神社で行う儀式を指し、ご自分の身についている厄(穢れ・邪気)を払っていただく意味合いがあります。
「厄除け」はお寺で行う儀式を指し、全国にある「厄除け大師」をはじめ、密教系の寺院で行う護摩祈祷が有名です。
厄払いとは異なり、1年間災厄が降りかからないように予防的に行う意味合いがあります。
どちらの方がご利益がある、といったことは無く、両方受けても問題はないので、ご自身の参拝しやすい寺社に参拝祈願しましょう。
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
合わせて読みたい