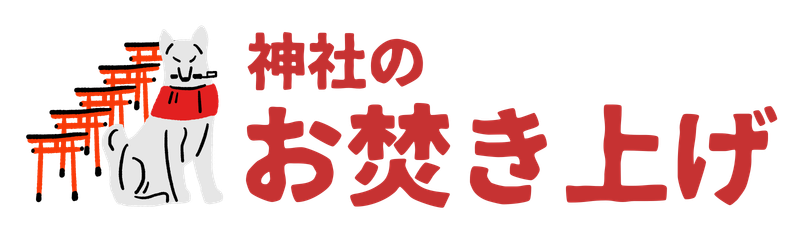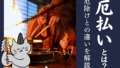人生で災難が降りかかりやすいとされる厄年。厄年は本厄と前厄・後厄の計3回ありますが、いずれも神社やお寺で厄払い(厄除け)を行うことで、穢れや邪気を祓い、災いを防ぐことができると言われています。
滋賀県内には、「厄除大祭」が毎年2月に催される田村神社をはじめ、「左義長まつり」と「八幡まつり」の2つの火祭りで有名な日牟禮八幡宮、陰陽道による厄除けのご利益で有名な賀茂神社など、厄払い(厄除け)のご利益で有名な神社・お寺があります。
本記事では、滋賀県内で厄払い(厄除け)を検討している方に向けて、県内の最強スポットを詳しくご紹介します。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
田村神社|甲賀市土山町

田村神社は、甲賀市に鎮座する坂上田村麻呂を主祭神としてお祀りする812年に創建された神社です。
坂上田村麻呂は、蝦夷征伐等の功績で知られる平安時代の有名な征夷大将軍です。
社伝によると、桓武天皇が坂上田村麻呂に鈴鹿峠の悪鬼を平定するよう勅命を出し、たちまち悪鬼を退治したとあります。そしてお亡くなりになった翌年、嵯峨天皇は勅令を出して坂上田村麻呂を現在の地に祀りました。そして疫病が流行していたため、嵯峨天皇は詔を出し、坂上田村麻呂の霊験を以て3日3晩に渡る厄除の大祈祷が斎行され、疫病が鎮まったとされます。
これにより、坂上田村麻呂は厄除の祖神として崇敬されることとなりました。
今でも毎年2月17日から19日の3日間に渡る「厄除大祭」(田村まつり)が催されます。
大祭では厄年の厄除けのご祈祷をはじめ、田村麻呂公のお告げによって境内を流れる御手洗川に豆を流すことで厄が落ちるとされる「厄豆落し」の神事が行われます。参拝に訪れた人たちは年齢と同じ数の福豆を川に流すことで厄を払います。
また田村神社では、毎年年末から厄除大祭前まで、本殿前に矢を2本交差させた長さ11メートルの大神矢が設置されます。下を潜ると厄が落とせるとされています。
通常の開運厄除祈祷も無休で奉仕しています。食べれば災厄除けができるとされる「かにが坂飴」が名物です。
| 料金 | 初穂料:5,000円、7,000円、10,000円、20,000円 特別祈祷初穂料:30.000円以上 |
| 授与品 | 祈祷後の授与品:大麻と神矢 厄落としの福豆一袋:200円 厄除御守:1000円、厄除箸:500円、赤の厄除け神矢:3,000円かにが坂飴 |
| 受付時間 | 厄除大祭中:7:00~20:00 正月大祈期間:1月1日 0:00~17:00、1月2日~7日:8:30~16:30 通常:9:00~16:30 |
| 予約/申込方法 | 直接祈祷受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | – |
田村神社
住所:滋賀県甲賀市土山町北土山469
公式HP:http://tamura-jinja.com/
立木神社|草津市草津

立木神社は、滋賀県の草津市に鎮座する厄除開運・交通安全の神社として信仰を集めている767年創建の古社です。
主祭神は、武甕槌命です。武甕槌命が、道中に手に持たれていた柿の鞭を社殿近くに刺したところ、柿の木は生え付き枝葉が茂り出しことから、里人がこの木を崇め、社殿を建てたことから社名を立木神社と称したと伝わっています。
武甕槌命は、悪疫を退散させ平和をもたらす布都御魂剣を授けることで、神武天皇の国造りを助けた神様で、厄除けのご神徳があります。
また、征夷大将軍の坂上田村麿が、東北鎮圧に際して、道中安全と厄除開運を祈願した霊験に由来し、厄除開運・交通安全の守護神として崇敬を集めています。
通年で厄除開運の祈祷が行われ、また毎年2月3日に行われる「節分大祭」では、厄除御祈祷が大々的に行われます。
| 料金 | 祈祷料:6,000円~ |
| 授与品 | 祈祷後の授与品:情報なし 節分大祭:福豆、福銭 (無料)、通常:厄除守 |
| 受付時間 | 厄除大祭:8:30~18:00 通常:9:00~16:00 |
| 予約/申込方法 | 厄除大祭での厄除祈祷:予約なしで随時受付 通常:事前予約要 |
| 注意事項 | – |
立木神社
住所:滋賀県草津市草津4-1-3
公式HP: https://tatikijinja.net/
長濱八幡宮|長浜市宮前町

長濱八幡宮は、日本三大山車祭の「長浜曳山祭」で有名な長浜市にある神社です。1069年に、源義家が後三条天皇の勅願を受け、京都の石清水八幡宮より分霊を迎えて創建されました。
御祭神は、応神天皇(誉田別尊)、仲哀天皇(足仲彦尊)、神功皇后(息長足姫尊)です。中でも、足仲彦尊は厄除け開運の神様、誉田別尊は厄除け開運、健康長寿の神様と呼ばれている厄除けで有名な神社です。
長濱八幡宮では、毎年1月18日から29日に、「新玉の厄逃れ特別祈祷」を催していて、期間中のみ「厄除け腕輪」を授かることが出来ます。
| 料金 | 祈祷料:5,000円~ |
| 授与品 | 新玉の厄逃れ祈祷の授与品:厄除け腕輪 あ、うん守り |
| 受付時間 | 9:00~ |
| 予約/申込方法 | 直接祈祷受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | – |
長濱八幡宮
住所:滋賀県長浜市宮前町13-55
公式HP: http://www.biwa.ne.jp/~hatimang/
豊圀神社 (厄除八幡宮)|東近江市池庄町
豊圀神社は、6世紀半ばに創祀されたとされる「厄除八幡宮」「厄神さん」と呼ばれる東近江市に鎮座する神社です。
御祭神は、応神天皇(誉田別尊)、神功皇后(息長足姫尊)、竹内宿彌大臣です。
豊圀神社は、毎年1月18日、19日、20日の3日間で厄除大祭が行われることで有名で、3・4万人の参拝客と数千人が祈祷を受けに訪れるため、大変な賑わいとなります。
江戸時代、当時の領主であり、出羽国山形の城主でもあった最上義智公が、1月19日を吉日として厄除け祈願を行ったことが由来と言われています。
| 料金 | 祈祷料:3,000円~ |
| 授与品 | 厄除け大祭:お神酒、お守り、おさがり(祈祷料により内容が変わります) 厄除け守り |
| 受付時間 | 厄除け大祭中:8:00~20:00 |
| 予約/申込方法 | 直接祈祷受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | – |
豊圀神社
住所:滋賀県東近江市池庄町1518
公式HP:https://www.toyokunishrineshiga.com/
賀茂神社|近江八幡市加茂町

近江八幡市に鎮座する賀茂神社は、736年に度重なる厄災を鎮めるため、聖武天皇が陰陽道の祖、吉備真備に勅命を下し、陰陽道を駆使して、当地を選び定め、賀茂大神を祀り創建されました。
御猟野乃杜賀茂神社とも呼ばれます。
一般の神社の場合本殿の向きは南向きか東向きですが、陰陽道で創建されたため、本殿が北東(表鬼門)という特殊な方位にあり、それにより本殿の向いている方位が南西(裏鬼門)になっています。
創建の所以から森羅万象の「気」が集まる聖地として、また陰陽道による、あらゆる災厄を封じ、人の進むべき道を導く神様として厄除け、鬼門封じ、方除けの神様として信仰されています。
日本初の国営牧場が置かれたことから、創建当初より馬との関わりが深く、「馬の聖地」としても崇敬が寄せられています。
| 料金 | 初穂料:8,000円~ |
| 授与品 | 祈祷後:お札、お守り 厄除け祈願セット(お札や絵馬、お守り、お箸など):2,500円 厄除け祈願札:1,000円 |
| 受付時間 | 9:30~16:00 |
| 予約/申込方法 | 直接祈祷受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | 遠方で来社できない場合は、依頼祈祷あり |
賀茂神社
住所:滋賀県近江八幡市加茂町1691
公式HP : https://kamo-jinjya.or.jp/
日牟禮八幡宮|近江八幡市宮内町

日牟禮八幡宮は、近江八幡に鎮座する131年に創建された八幡山の麓にある古社です。
地元では八幡様と親しまれる日牟禮八幡宮は、八幡さまが祀られていたことが、八幡の地名となり、今の「近江八幡市」の市名の由来となりました。
御祭神は、応神天皇(誉田別尊)、神功皇后(息長足姫尊)、比賣神(宗像三女神)です。応神天皇は、八幡大神として「厄除開運の神様」として広く信仰されています。
1590年に関白豊臣秀次が八幡山に城を築き、琵琶湖の水を引き入れて八幡堀を開削して水運を高め、城下町を発展させ、商人の街に発展しました。 八幡城廃城後は、近江商人として全国に商いに出かけました。それにより日牟禮八幡宮は近江商人の「厄除開運」「商売繁盛」の守護神として広く崇敬を集めるようになりました。
国の選択無形民族文化財の2大火祭り「左義長まつり」(3月)と「八幡まつり」(4月)で有名な神社でもあります。
2月3日の節分祭では、厄除け祈祷が盛大に行われます。還暦、本厄の方は、豆まきを行い、1年の厄を祓い、心身を清めます。
| 料金 | 豆まき奉仕料・祈祷料:15,000円より、祈祷料:5,000円/ 10,000円~ 通常祈祷料:5,000円~ |
| 授与品 | 節分祭:厄除祈祷符 |
| 受付時間 | 節分祭:8:30~20:00 通常:8:30~16:00 |
| 予約/申込方法 | 豆まき奉仕:直接社務所で申し込み(1月31日まで) 通常:直接社務所で随時申し込み |
| 注意事項 | – |
日牟禮八幡宮
住所:滋賀県近江八幡市宮内町257
公式HP: https://himure.jp/
立木山安養寺 (立木観音)|大津市石山南郷町

立木山安養寺は、大津市の鹿跳渓谷にある平安時代初期の815年に弘法大師が開いた浄土宗のお寺です。「立木観音」として知られています。
弘法大師が42歳の厄年に、白い鹿に導かれ見つけた光る霊木を、立木のまま背丈に合わせて観世音菩薩像を刻み建立した「厄除けの寺」として広く信仰されています。
本堂までは石段が約800段続き、さらに石段を上ると厄徐の鐘と呼ばれる鐘楼があります。心をこめてゆるやかに一撞きすると煩悩や厄を払うことができるとされます。
厄除け祈願は毎日行われ、祈願の受付後、祈願法要を行い満願の御符が10日程で郵送されます。
| 料金 | 祈願料:3,000円(普通祈願)、5,000円(特別祈願)、10,000円~(特別大祈願) |
| 授与品 | 祈願後:御符 金襴御守:1,000円、御守:800円、厄除け箸 |
| 受付時間 | 9:00~ |
| 予約/申込方法 | 直接寺務所受付で申し込み、また郵送による申し込み |
| 注意事項 | – |
立木観音(立木山安養寺)
住所:滋賀県大津市石山南郷町奥山1231
公式HP: https://www.tachikikannon.or.jp/
日吉大社|大津市坂本

日吉大社は、比叡山麓に鎮座する古事記にも登場する古社で、崇神天皇の時代の紀元前91年に比叡山の神、大山咋神を麓に迎え創祀されたとされる全国3800社の日吉・日枝・山王神社の総本宮です。
平安京遷都の際には、京都御所の表鬼門の方角(北東)にあたることから方位除け祈願の社とされ、都の魔除・災難除を祈る守護神として信仰されてきました。「魔除け・厄除け」のご利益で知られています。
御祭神は、境内にある約40のお社があり、全ての神様を総称して「日吉大神」と呼びます。 国宝の本殿の他にも多くの建造物が重要文化財に指定されています。
日吉大社では、神様のお使いとされる「神猿(まさる)」が魔除けのシンボルとして大切にされ、境内の色々なところに祀られています。「魔去る」「勝る」にかけて縁起がいいとされ、魔除けや厄除け・必勝のご利益があるとされ親しまれています。
日吉大社では、厄除けの祈祷を毎日西本宮拝殿にて行なっています。
| 料金 | 初穂料:5,000円~ 下殿特別祈祷:20,000円 |
| 授与品 | 祈願後:祈願札、お守りなどのおさがり、お神酒 神猿みくじ:500円(茶)800円(金)、厄除守:1000円、神猿守:1000円 |
| 受付時間 | 9:00~16:00 (年中無休) |
| 予約/申込方法 | 直接西本宮授与所で申し込み |
| 注意事項 | – |
日吉大社
住所:滋賀県大津市坂本5丁目1-1
公式HP: https://hiyoshitaisha.jp/
竜王観音(観音禅寺)|蒲生郡竜王町
観音禅寺は、853年に創建されたとされる大津市にある臨済宗妙心寺派の禅寺です。「竜王観音」の名で親しまれています。
ご本尊は、聖徳太子が28歳のときに一刀三礼して彫ったと伝わる 十一面観音大菩薩 (厄除竜王観音)です。60年に一度の大開張、30年に一度半開帳される秘仏です。
ご本尊は、戦の兵火で全山が焼け落ちても、そのたびにこの観音様だけは焼け残ってきたため、厄除けのご利益があると信仰されてきました。
竜王観音では、土でできた厄除け玉に息を三度吹きかけて、開運浄石に投げつけて、厄落としができる神事があります。また厄除開運、厄払いのご祈祷も授与できます。
| 料金 | 志納金:5,000円(普通祈願)、10,000円(通常祈祷)、30,000円以上(特別祈祷) |
| 授与品 | 祈願後:祈願札 厄除け玉:200円 |
| 受付時間 | 午前9:00~12:00 午後13:00~16:00 |
| 予約/申込方法 | 予約が望ましい |
| 注意事項 |
|
竜王観音(牟禮山 観音禅寺)
住所:滋賀県蒲生郡竜王町小口848
公式HP:https://www.kannonzenji.com/
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら