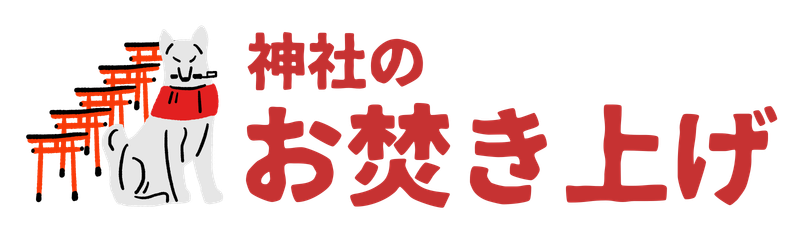人生で災難が降りかかりやすいとされる厄年。厄年は本厄と前厄・後厄の計3回ありますが、いずれも神社やお寺で厄払い(厄除け)を行うことで、穢れや邪気を祓い、災いを防ぐことができると言われています。
京都府内には、厄除けのお祭り「祇園祭」で知られる八坂神社をはじめ、八幡御神矢のご利益で知られる石清水八幡宮、節分厄除詣発祥の地と言われる吉田神社など、厄払い(厄除け)のご利益で有名な神社・お寺があります。
本記事では、京都府内で厄払い(厄除け)を検討している方に向けて、県内の最強スポットを詳しくご紹介します。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
八坂神社|京都市東山区祇園町

八坂神社は、656年に素戔嗚尊を祀ったのが起源とされる古社です。素戔嗚尊は、ヤマタノオロチを退治したあらゆる災いを祓う神様で、疫病除け・厄払いのご利益のある神社として信仰されています。
全国に2300あるという八坂神社や素戔嗚尊を祭神とする神社の総本社です。本殿は国宝で摂社・末社、建造物29棟は重要文化財として指定されています。
古くから「祇園さん」と親しまれ、祇園の芸舞妓さんたちもお参りに訪れる、祇園のシンボル的神社です。
毎年7月に開催される日本三大祭りの1つの「祇園祭」は、869年に疫病が鎮まるようにとの祈りを込めて始まった八坂神社の祭礼で、厄除けのご利益を今に伝えています。
厄払い(厄年払い)のご祈祷と災難除けの御祈祷があります。授与品としては厄除開運守があり、また祇園祭の時期には厄除ちまきが授与されます。
| 料金 | 初穂料:8,000円~ 15,000円以上:巫女の神楽舞がつきます。 |
| 授与品 | 撤下品:御札・御守・御神酒・乾物物、厄除開運守:1,000円、厄除ちまき:1,500円 |
| 受付時間 | 9:00~16:00 |
| 予約/申込方法 | 直接祈願受付所で随時申し込み |
| 注意事項 |
|
八坂神社
住所:京都府京都市東山区祇園町北側625
公式HP:https://www.yasaka-jinja.or.jp/
上賀茂神社|京都市北区上賀茂本山

上賀茂神社は、神武天皇の御代に創始され、677年に社殿が創建されたとされる京都で最も古い神社の1つです。正式名は、賀茂別雷神社です。
神武天皇の御代に本殿から北北西に位置する神山に降臨された「賀茂別雷大神」を御祭神としています。 賀茂別雷大神は、雷を裂くほどに強い力で災いを払い除けて運を開いて下さるとされる雷の神様とされ、厄除・災難除け・必勝の神として信仰されています。
神社全体が世界文化遺産に認定され、境内には2棟の国宝と41棟の重要文化財が点在しています。1,500年前に飢饉と疫病を鎮めるために始まったとされる京都三大祭りに数えられる「葵祭」でも有名な神社です。
境内には、細殿の前に盛られた一対の「立砂」があります。 賀茂別雷大神が降臨した神体である神山を模したもので、御祭神が降臨を象徴する依代です。
この立砂は、盛り塩や、鬼門にまく清めの砂の起源とされ、強力な厄除けや災難除けのご利益があるとされます。
厄除、方除、雷除の御祈祷があり、授与品には、清めの砂(斎砂)、厄除守があります。
毎年お正月三が日に、上賀茂神社では無病息災・厄除け祈願として「大根炊き」が行われ、「厄除け大根」、「厄除けぜんざい」が振る舞われ、多くの参拝客が訪れます。
| 料金 | 初穂料:5,000円~ |
| 授与品 | 祈祷後の授与品情報なし、厄除御守:800円、斎砂:500円 |
| 受付時間 | 9:00~16:00 |
| 予約/申込方法 | 直接祈願受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | 本殿にて祭典を行なっている時はご祈祷はできません 郵送祈祷があります (6,000円〜) |
賀茂別雷神社(上賀茂神社)
住所:京都府京都市北区上賀茂本山339
公式HP:https://www.kamigamojinja.jp/
晴明神社|京都市上京区晴明町

晴明神社は、平安時代の陰陽師の安倍晴明公を祀る神社です。
安倍晴明公は、当時の天文暦学から独特の「陰陽道」を確立し、朝廷の祭政に貢献しました。晴明公が亡くなると、時の一条天皇はその遺業を賛え、屋敷跡に晴明を祀る神社を1007年に創建したものです。
晴明神社は、「魔除け」「厄除け」の神社で、晴明公が考案した魔除け・厄除けの象徴である五芒星のご神紋が随所に見られます。
境内には陰陽道で魔除厄除の果物とされた桃の像「厄除桃」があります。 桃の像に触れ自身の厄を桃になでつけることで、厄を落とすことができるとされています。
厄年の厄除け祈願、災難除け祈願が有名です。授与品には、五芒星のシンボルの入った厄除守そして正五角形の魔除け絵馬、魔除水晶守などがあります。
晴明神社では、「陰」から「陽」へ「気」が変わる1年の節目の日に穢れを祓う祭儀が節分星祭として行われます。 参拝者は「ひとがた」という人の形を模した紙に息を吹きかけ、自らの穢れを移して、歳の数だけお豆をいれた袋と一緒に神前に納めます。四方の魔を矢で追い払う儀式「追儺の儀」をおこなった後、納めた人形と年豆を焚き厄を落とします。
| 料金 | 初穂料:6,000円、8,000円、10,000円~ |
| 授与品 | おさがり:お札、お守り(初穂料によって授与品の内容が変わります) 厄除守:1200円、魔除水晶守:4,500円 |
| 受付時間 | 9:00~17:00 |
| 予約/申込方法 | 1週間前より電話で予約: 075-441-6460 |
| 注意事項 | 郵送祈祷もあります。6,000円〜 |
晴明神社
住所:京都府京都市上京区晴明町806
公式HP:https://www.seimeijinja.jp/
北野天満宮|京都市上京区馬喰町

北野天満宮は、創建947年の学問の神様で知られる菅原道真公を祀る、太宰府天満宮とともに全国約1万2,000社の天満宮・天神社の総本社の1つです。
「北野の天神さま」と呼び親しまれ、入試合格・学業成就・文化芸能などの学問的なご利益だけでなく、災難厄除のご利益でも篤く信仰されています。
北野は、平安京の北西の角の怨霊や恐ろしいものが出入りする天門という方位にあり、道真公の怨霊を鎮める力が働き、厄を払い、逆に運気が上昇すると信じられていると言われます。そのため、北野天満宮には、毎年多くの参拝客が厄除祈祷に訪れます。
北野天満宮の授与品の1つに厄除割札があります。割符には、前厄、本厄、後厄用と、災難厄除用があり、木片を2つに割り、片方を北野天満宮に納め、片方をお守りとして持ちます。 厄除守もあります。
道真公の祥月命日である2月25日には、梅の花をこよなく愛でた道真公を偲び、御本殿に「梅花御供」を供え、厄を祓う祭典・梅花祭が斎行されます。祭典で用いた玄米は「厄除玄米」として授与されます。
| 料金 | 初穂料:5,000円、8,000円、10,000円、10,000円以上(特別祈祷) |
| 授与品 | 撤下神饌: 5,000円(御神札・撤饌) 8,000円(御神札・撤饌・大福小梅) 10,000円(御神札・撤饌・御神梅酒・大福小梅) 厄除守:1,000円、厄除割札:500円 |
| 受付時間 | 9:00~16:30 |
| 予約/申込方法 | 直接祈願受付所で随時申し込み |
| 注意事項 |
北野天満宮
住所:京都府京都市上京区馬喰町
公式HP:https://kitanotenmangu.or.jp/
吉田神社|京都市左京区吉田神楽岡町

吉田神社は、平安京の守護神として、奈良の春日大社の四柱(建御賀豆智命、伊波比主命、天之子八根命、比売神)を勧請し、都の東北「鬼門」に位置する吉田山の麓に859年に創建された神社です。
御祭神の健御賀豆知命と伊波比主命は、諸々の災難より逃れ幸福を勝ち取る厄除・開運の神で、また平安京の守護神として創建されたことから、吉田神社は導き厄除け開運の神様として崇敬されてきました。
吉田神社の節分祭は、平安朝初期から宮中で行われていたものを古式に則って継承する室町時代から続く神事で、京都の節分行事として特に有名です。
吉田神社の節分祭によって現代の節分祭の原型となる神事が社寺へと広まったとされ、節分厄除詣発祥の地とも言われています。
2月3日の節分当日を中心に前後3日間にわたって行われる祭事には、疫神祭、追儺式(鬼やらい神事)、火炉祭などがあり、例年50万人以上の参拝者が訪れます。
期間中には、厄塚が設けられ、触ることで厄を塚に封じ込め、厄除け開運祈願をすることができます。また魔除けの力のある梔子色の神札神符が授与されます。
厄除祈願に多く人々が訪れる神社です。授与品には厄除錦守 、魔除開運守があります。
| 料金 | 初穂料:5,000円(当日祈祷)、10,000円(1ヶ月祈祷)、15,000円(1年祈祷) |
| 授与品 | 祈祷後の授与品;御神札 厄除錦守 、魔除開運守 |
| 受付時間 | 9:00~16:20 |
| 予約/申込方法 | 直接祈願受付所で随時申し込み |
| 注意事項 | 1月1日及び節分期間は受付時間が変わります |
吉田神社
住所:京都府京都市左京区吉田神楽岡町30番地
公式HP:https://www.yoshidajinja.com/index.html
神光院|京都市北区西賀茂神光院町

神光院は、弘法大師空海が42歳の厄年に厄除けの修法をした真言宗のお寺です。弘法大師ゆかりの寺院として東寺と仁和寺とともに「京都三大弘法」の一つにも数えられています。
弘法大師が90日の修行を終えお寺を離れる時、別れを惜しむ村人達に「私の教えを信じる者はすべての諸病災厄を免れるであろう」と言って境内の池に映る自分の姿を木像に彫って残されたと伝わる本尊があり、「厄除け大師」として広く信仰を集めています。
毎年7月21日と土用丑の日に諸病封じの「きうり加持(きゅうり封じ)」が行われます。弘法大師空海がきゅうりに病魔を封じ込め五智不動尊に病魔平癒を祈願したという故事にちなんで、きゅうりによる疫病除けの祈祷が厳修されます。
神光院
住所:京都市北区西賀茂神光院町120
公式HP:https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=9&tourism_id=26 (京都観光公式サイト)
石清水八幡宮|八幡市八幡高坊

石清水八幡宮は「やわたの八幡さん」と親しまれる京都府南部の八幡市に鎮座する平安時代860年に創建された国家鎮護の大社です。日本三大八幡宮の1つに数えられ、歴代朝廷や武家からの崇敬を集めてきました。
石清水八幡宮は、京都の裏鬼門とも呼ばれる南西の方角にあたる男山山頂に社殿が建立され、都を守護してきました。
御祭神は、応神天皇、比咩大神 、神功皇后の八幡大神です。 応神天皇の厄除けのご神徳と都の守護神として、古くから災厄を除ける神様として信仰を集めてきました。
石清水八幡宮では、祈祷に合わせて、八幡大神の霊力の象徴である「邪悪な敵を打ち払い、ただしきを守り、狙った的に必ず当たる」とされる「八幡御神矢」を授与し、御神矢を手にとって厄除け祈祷を受けます。
毎年1月15日から19日までの期間中、厄除開運祈願が執り行われ、期間限定の厄除大祭札が授与されます。19日には火で清められた厄除開運餅が授与され、毎年長蛇の列ができます。
また節分の時期には厄除け祈願を兼ねた年男と年女による豆まきの「鬼やらい神事」が斎行されます。
厄除開運祈願には、厄年厄除け祈願、八方除祈願、方除祈願、災難除祈願があります。 厄除開運守りも多く、厄除開運袋守、七色守、金矢守などがあります。
| 料金 | 初穂料:10,000円~ |
| 授与品 | 八幡御神矢:3,000円、特別厄除御神矢:5,000円、八幡御神弓:8,000円 |
| 受付時間 | 9:00~16:00 (年末年始は変動) |
| 予約/申込方法 | 直接祈願受付所で随時申し込み |
| 注意事項 |
|
石清水八幡宮
住所:京都府八幡市八幡高坊30
公式HP:https://iwashimizu.or.jp/
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら