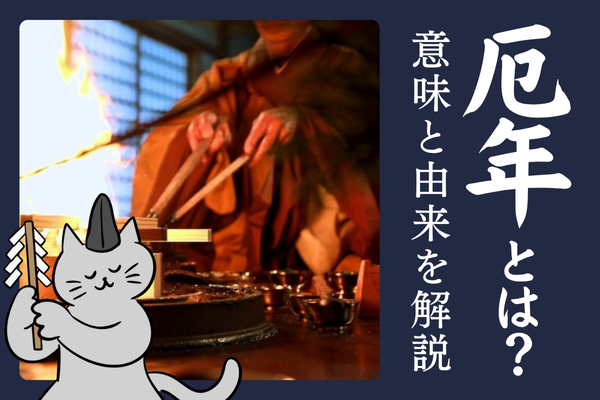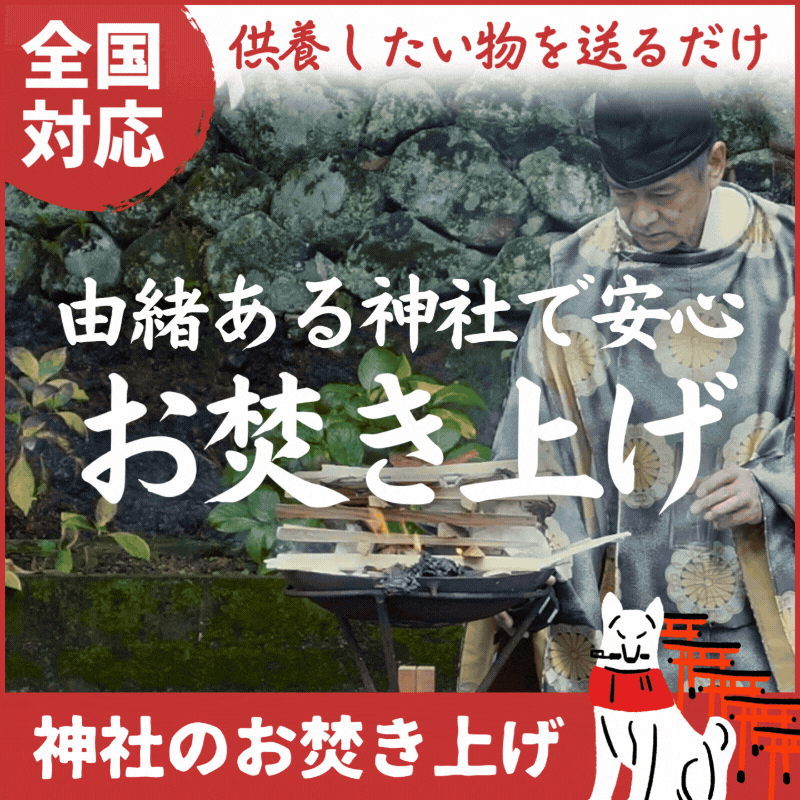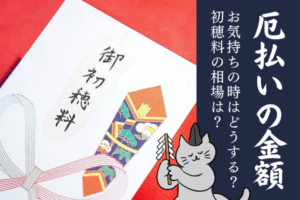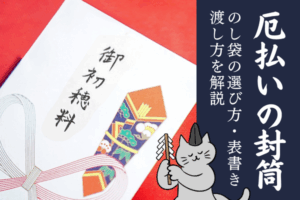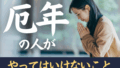厄年は俗に「災いや不幸に見舞われやすい年」とされていますが、その歴史は古く平安時代に遡ると言われています。
厄年には前厄・本厄・後厄・本厄、合計4つの呼び名がありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
本記事では、厄年の意味と由来、種類、方位除け(八方塞がり)との違いについて詳しく解説します。
厄年の意味を正しく理解し、平穏な一年を過ごしましょう。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
厄年とは?

厄年とは、遥か昔から日本で信じられてきた信仰・言い伝えの一種で、「災い・不幸に見舞われやすい年齢」を指す言葉です。
厄年の「厄」という漢字には、災難・災い・困難といった意味があります。
厄年にあたる一年間は、病気・怪我などのトラブルに遭いやすいため特に気をつけて過ごす必要があり、神社やお寺で厄払い(厄除け)祈願を受けるのが通例となっています。
厄年の起源には諸説ありますが、昔は平均寿命が短かく、医療も発達していなかったため、厄年にあたる年齢は、命に関わる怪我や病気に見舞われるリスクが高かったことが、こうした信仰の土台になったと考えられます。
厄年の他にも人生の節目に関する風習として「七五三」や「十三詣り」などが現在も残っています。
厄年の年齢は古くから変わっていないため、高齢・晩婚化が進む現代では受け止め方や印象が異なりますが、結婚・出産・転職・引越しなど人生の転機と重なることも多く、現代においても人生の節目として大切に過ごす必要があると言えるでしょう。
女性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 32歳 | 33歳 ★大厄 | 34歳 |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
女性の厄年は人生で4回あり、19歳、33歳、37歳、61歳が本厄。33歳が大厄にあたります。
男性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 41歳 | 42歳 ★本厄 | 43歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
男性の厄年は人生で3回あり、25歳、42歳、61歳が本厄。42歳が大厄にあたります。
厄年の数え方
厄年は、日本の古い年齢の数え方である「数え年」を基準に数えます。
数え年では、生まれたときが1歳で、元日を迎える度に年齢が加算されます。
満年齢とは1、2歳の差が生じるため、厄年を確認する際は「生まれ年」で確認するのがおすすめです。
前厄・本厄・後厄・大厄の意味と違い
| 前厄 | 厄の兆候が現れる年齢 |
| 本厄 | 最も災難に見舞われやすい年齢 |
| 後厄 | 厄が徐々に薄らいでいく年齢 |
厄年は一般的に「本厄」とその前後にある「前厄」「後厄」の3年間を指します。
前厄は、さまざまな変化の兆候が表れ始めるタイミングで「厄年入り」とも呼ばれます。
また、本厄の翌年にあたる後厄は「厄晴れの年」とも呼ばれます。
「大厄」とは、人生に訪れる厄年の中でも「最も災いが降りかかりやすい年齢」とされており、数え年で男性の42歳、女性の33歳が本厄にあたります。
42歳は「死に」、33歳は「散々」という語呂合わせに由来するという説もありますが、この年齢は人生の転換期にあたることが多く、心身の不調を感じやすいため、特に慎重に過ごすことが大切です。
厄年の由来と歴史
厄年の歴史は古く、中国から朝鮮半島を経て、平安時代に日本に伝わった陰陽五行説に基づいた陰陽道を起源とする説が有力です。
平安時代には陰陽道の影響を受けた儀式が貴族の間で行われるようになり、『源氏物語』の若菜下巻には、紫の上が37歳の厄年に加持祈祷を受け、物忌みをするくだりが記されています。
厄年の風習は、室町時代には武家社会の間で広まり、江戸時代に入ると庶民の間でも厄払い(厄除け)祈願が行われるようになりました。
厄年の年齢は年代によって異なり、現在使われている年齢は江戸時代に定められたものです。
神道では、厄年を迎えた男性が氏子集団に加入し、神社の祭祀や神輿担ぎなどの神事を担う、という風習が古くからあり、神事に関わる男性は心身を清め物忌(ものいみ)に服する必要がありました。
神主をはじめ神さまにお仕えする人のことを「神役(しんやく)」といい、厄年の「厄」が神役の「役」であるといわれるのも、こうした理由によるものです。
方位除け(八方塞がり)との違い

厄年と混同されやすいのが方位除け(八方塞がり)です。
「八方塞がり」とは、中国を起源とする九星気学において、9年に1度巡ってくるどの方角に進んでも不運が続くとされる時期です。
生まれた年によって9つの「本命星(生まれ星)」が決められており、本命星が方位盤の中央に位置し、他の八つの星が全ての方向を遮り、どの方角に事を起こしても出口がない状態(大凶方位)を八方塞がりといいます。
本命星が八方塞がりにあたる年は、病気・ケガ・事故・トラブルなど不幸が起きやすく、方位除けの祈願を受けるのが通例となっています。
八方塞がりの年となるのは、数え歳で十の位と一の位の数字を足して10になる歳、たとえば19歳、28歳、37歳、46歳、55歳、64歳、73歳などが該当します。
年齢を軸にする厄年とは異なり、八方塞がりは本命星と方位盤上の配置によって決まります。また、八方塞がりは男女共通であることも大きな違いです。
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
合わせて読みたい