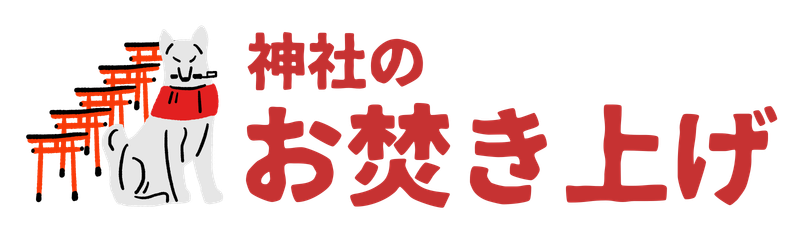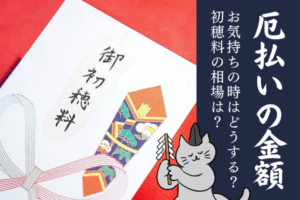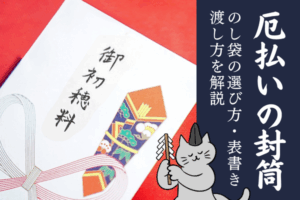厄年は「災いや不幸に見舞われやすい年」とされており、日本では古くから、厄年に当たる年に神社やお寺に参拝し、厄払い(厄除け)祈願を行う風習があります。
神仏習合の時代を経て、現代において「厄払い」と「厄除け」はほぼ同義で扱われていますが、本来は異なる意味を持つ言葉です。
本記事では、厄払いと厄除けの意味と違い、厄落としの意味を詳しく解説します。
厄払いの意味を正しく理解し、平穏な一年を過ごしましょう。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
厄払いとは?厄除けとの違い

「厄払い」は主に神道で使われる言葉で、神社で行う祈祷を指します。
厄払いは本来、身の回りで既に起きている災厄を取り除き清めるための儀式であり、自身についた穢れや邪気を祓うために行います。
そのため不幸や災いが続く時は、厄年以外の人も厄払い祈願を受けることができます。
対して「厄除け」は主に仏教で使われる言葉で、お寺で行う護摩祈祷・祈願を指します。
厄除けは、悪いことや災いが寄ってこないよう予防的に行う儀式で、清めた体に厄を寄せ付けないよう祈願します。
密教系の寺院で行われる護摩祈祷が特に有名で、日本各地に「厄除け大師」と呼ばれるお寺があります。
厄払い(厄除け)祈願はいつ受けるのが正解?
厄払い(厄除け)祈願を行う時期に明確な決まりはなく、ご自身の好きなタイミングで参拝祈願して問題ありません。
一般的には立春までに行うのが習わしとなっており、1月1日の元旦から節分(2月3日)にかけて、厄払い祈願の参拝者で多く賑わいます。
全国の神社・お寺では通年で厄払い祈願を受け付けているので、年始に限らず、ご自身の誕生日や、何か不幸や心配事があった際には祈願を受けると良いでしょう。
厄払い(厄除け)祈願は神社とお寺どちらで受けるべき?
前述した通り、神社で行う厄払いとお寺で行う厄除けは儀式や意味が異なるため、どちらの方がよりご利益がある、といったことはなく、両方受けても問題はありません。
祈願を受けるタイミング・回数も明確な決まりはないので、ご自身の参拝しやすい寺社に参拝祈願しましょう。
厄払い祈願(神社)の流れ・参拝手順
神社で行う厄払いは、身についた厄(災い・穢れ)を祓い落とし、災厄から身を守っていただけるよう神様に祈る儀式です。
一般的な厄払いの儀式の流れは以下の通りです。
| 手水で身を清める | 境内に入ったら、手水舎で手と口を洗い清めます |
| 拝礼 | 本殿で「二礼二拍手一礼」で神様に願いを込めて拝礼します |
| 受付と支払い | 受付で厄払いを申し込み、祈祷料(初穂料)を支払います |
| 儀式の開始 | 神職が祝詞を奏上し、参列者の身を清めるためにお祓いをします |
| お祓い | 「大麻」と呼ばれる祓具で、参列者の身を振るって清めます |
| 玉串拝礼 | 儀式の最後に、玉串を神前に捧げます。参加者自身が行う場合と神職が代行する場合があります |
| 御札・お守りの授与 | 儀式後に、厄除けのお札やお守りが授与されます |
厄除け祈願(お寺)の流れ・参拝手順
お寺で行う厄除けは、災厄が自分の身に降りかからないよう御本尊(不動明王/弘法大師/元三大師など)に祈る儀式で、護摩祈祷を行うのが一般的です。
護摩祈祷は、護摩壇に護摩木を人間の煩悩とし燃やして煩悩を焼き清め、その聖なる炎の力で厄を祓う意味合いがあります。
一般的な厄除けの儀式の流れは以下の通りです。
| 受付 | 寺院の受付で厄除けを申し込み、祈祷料(初穂料)を支払います |
| 護摩木への記入 | 護摩木に願い事や名前などを記入します |
| 護摩祈祷 | 僧侶が護摩壇に火をつけ、お経を唱え、護摩木を燃やします |
| 御護摩札の授与 | 護摩祈祷の後、御護摩札やお守りなどが授与されます |
厄落としとは?

厄落としは日本で古くから伝わる呪いの一種で、自分で災厄を引き起こすことで、これ以上災いが起きないようにする行為を指します。
今まで大切にしてきた物や、普段身に着けている物や大切な物を意図的に落とすことで、自身に降りかかる厄を落とすことができると考えられています。
豊臣秀吉は自身の兄が早世したため、嫡男・秀頼が生まれた際に、生まれたばかりの秀頼を一旦捨てて、厄落としを行ったという逸話があります。
物を落とす他にも、
- 人に食事を振る舞う
- 高いところからお餅やお菓子をまく
- 赤飯を配る
など、地域によって様々な厄落としの風習があります。
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
合わせて読みたい