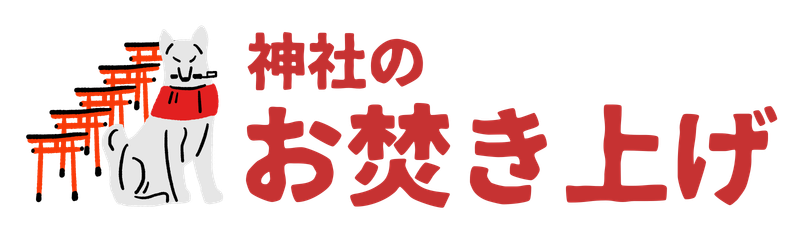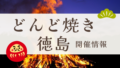お正月飾りやしめ縄、一年間災厄から守っていただいた御札や御守りをお焚き上げする「どんど焼き」は、どんど焼きの煙とともにお迎えした歳神様を天にお送りし、新年の無病息災や五穀豊穣を願う日本各地に伝わる小正月の伝統行事です。
奈良県内には、どんど焼きを行っているお寺・神社が数多くあり、観光地としても有名な東大寺、春日大社などでも開催されています。
石上神宮や吉祥草寺など、伝統行事として盛大に行われているところも多く、寺社ごとに様々な特色があるのも奈良という地域ならではの特徴です。
本記事では、奈良県内のどんど焼き開催情報を詳しくご紹介します。
*お焚き上げは、自社のもののみ受け付ける場合と、自社以外のものも受け付ける場合とがあるので事前に確認してください。
*悪天候等の理由により中止・延期となる場合があります。開催有無・日時を公式HPからご確認ください。
古い正月飾り・お守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、お品を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・プラスチックなど不燃物もOK
✅ 神棚・ひな人形など、お守り・縁起物以外もまとめて送れる
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
- 奈良県内のどんど焼き開催情報
- 信貴山朝護孫子寺「左義長(納め札焼大とんど)」|生駒郡平群町
- 東大寺「還宮」|奈良市
- 松尾寺「左義長」|大和郡山市
- 石上神宮「古神符焼納祭(大とんど)」|天理市
- 大神神社「大とんど」|桜井市
- 鹿嶋神社「どんど焼き(古神札焚上祭)」|香芝市
- 天神社「古神符焼上祭」|大和高田市
- 生蓮寺「とんど」|五條市
- 墨坂神社「神札焼上祭(とんど)」|宇陀市
- 転法輪寺「とんど供養」|御所市
- 千光寺「鳴川大とんど」|生駒郡平群町
- 龍田大社「大とんど」|生駒郡三郷町
- 天河大辨財天社「とんど祭」|吉野郡天川村
- 玉置神社「古神札御焚き上げ祭」|吉野郡十津川村
- 吉祥草寺「大とんど」|御所市
- 春日大社「春日の大とんど」|奈良市
- 自宅から送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ
奈良県内のどんど焼き開催情報
| 開催場所/イベント名 | 日時 | 参加方法 |
| 信貴山朝護孫子寺 | 毎年1月14日 | 持ち込み |
| 東大寺 | 毎年2月3日 | 年末から開催日前日までに二月堂へ持参 |
| 松尾寺 | 毎年1月15日 | 納札所に納める |
| 石上神宮 | 毎年1月15日 | 持ち込み |
| 大神神社 | 毎年1月15日 | 持ち込み |
| 鹿嶋神社 | 毎年1月15日 | 持ち込み |
| 天神社 | 毎年1月15日前後 | 持ち込み |
| 生蓮寺 | 毎年1月14日 | 納札所に納める |
| 墨坂神社 | 毎年1月15日 | 持ち込み |
| 転法輪寺 | 毎年成人の日 | 持ち込み |
| 千光寺 | 毎年1月第2日曜日 | 持ち込み |
| 龍田大社 | 毎年1月15日 | 持ち込み |
| 天河大辨財天社 | 毎年1月15日 | 納札所に納める |
| 玉置神社 | 毎年1月28日 | 納札所に納める |
| 吉祥草寺 | 毎年1月14日 | 持ち込み |
| 春日大社 | 毎年1月下旬 | 持ち込み |
※開催日時・参加方法・最新情報は公式HPをご確認ください
信貴山朝護孫子寺「左義長(納め札焼大とんど)」|生駒郡平群町
醍醐天皇の病気平癒の祈願をしたことから「朝護孫子寺」の勅号を賜った毘沙門天王の総本山・信貴山朝護孫子寺。
聖徳太子がご感得された毘沙門天王をご本尊にお祀りしています。
信貴山朝護孫子寺では、毎年1月14日に信貴山内で「左義長・納め札焼大とんど」が開催されます。
本堂でのお勤めののち、僧侶、行者の行列にて赤門下広場へ移動し、竜の形に作られた大きな松明に点火されます。
| 開催日時 | 毎年1月14日 18時〜 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
信貴山朝護孫子寺「左義長(納め札焼大とんど)」
住所:〒636-0923 奈良県生駒郡平群町信貴山
公式HP:https://www.sigisan.or.jp/
東大寺「還宮」|奈良市
華厳宗大本山東大寺は、「奈良の大仏」で有名な東大寺盧舎那仏像をはじめ、正倉院やお水取りで知られる二月堂など、数多くの国宝・重要文化財を所蔵するお寺です。
東大寺ではどんど焼きを「還宮」と呼び、毎年2月3日の10時頃から二月堂東南の飯道神社上の壇で還宮作法が厳修され、積み上げられたお守り・御札に点火されます。
| 開催日時 | 毎年2月3日 午前10時 |
| 受付方法 | 年末から開催日前日までに二月堂へ持参 |
| 注意点 | お問い合わせください |
東大寺「還宮」
住所:〒630-8587 奈良県奈良市雑司町406-1
公式HP:https://www.todaiji.or.jp/
松尾寺「左義長」|大和郡山市
松尾寺は、日本最古の厄除け霊場であり「厄攘」唯一の祈祷寺として知られています。
「厄攘」とは厄を盗んでもらうという意味です。
千の手と千の目をもつ厄除け観音・千手千眼観世音菩薩がご本尊として祀られています。
毎年1月15日に、神霊石の大岩の前、境内中央の護摩壇にて「左義長(とんど)」が執り行われます。
古い御礼やお飾りは通年で受け付けいますが、厳かな雰囲気で新年のスタートを迎えたい方は当日持ち込み参列してみてください。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前9時 |
| 受付方法 | 納札所に納める |
| 注意点 |
|
松尾寺「左義長」
住所:〒639-1057 奈良県大和郡山市山田町683
公式HP:https://matsuodera.com/
石上神宮「古神符焼納祭(大とんど)」|天理市
自然豊かな大和盆地の中央に位置する石上神宮は、健康長寿・病気平癒・除災招福・百事成就の守護神として信仰されています。
本殿に続く楼門や、当神宮の中でもっとも神聖な区域・禁足地から出土した宝物など、多くの重要文化財を有する日本最古の神社のひとつです。
毎年1月15日に行われる月次祭と出雲建雄神社例祭に続いて、「古神符焼納祭(大とんど)」が開催されます。
大勢の参列者が見守るなか、宮司以下全員で大祓詞を奏上する様子は圧巻です。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前10時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
石上神宮「古神符焼納祭(大とんど)」
住所:〒632-0014 奈良県天理市布留町384
公式HP:https://www.isonokami.jp/
大神神社「大とんど」|桜井市
古事記や日本書紀に創祀にまつわる伝承が記されている大神神社は、三輪山をご神体とするため本殿はなく、拝殿を通して直接三輪山に祈りを捧げます。その祭祀の姿から、大神神社は日本最古の神社と言われています。
祈祷殿前斎庭にて執り行われる「大とんど」では、ご神火によるお正月飾りや前年の御神札のお焚き上げが厳かに行われます。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前8時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
大神神社「大とんど」
住所:〒633-8538 奈良県桜井市三輪1422
公式HP:https://oomiwa.or.jp/
鹿嶋神社「どんど焼き(古神札焚上祭)」|香芝市
令和4年に鎮座850年を迎えた鹿島神社は、武勇に優れた軍神・武甕槌大神 (たけみかづちのおおかみ)を御祭神としてお祀りしている神社です。
源氏にいわれをもつ鹿島神社に奉納されている「だんじり」には、壇ノ浦の戦いをはじめとする源平の戦いが主題となった彫り物が全体に施され、参拝者の目を楽しませてくれます。
毎年1月15日に「どんど焼き(古神札焚上祭)」が執り行われ、同じ日に落語会も開催されています。落語会の後には焼いも、甘酒の振舞い接待もあります。
| 開催日時 | 毎年1月15日 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 |
|
鹿嶋神社「どんど焼き(古神札焚上祭)」
住所:〒639-0231 奈良県香芝市下田西1-9-3
公式HP:https://kashiba-no-kashima.org/
天神社「古神符焼上祭」|大和高田市
「高田の天神さん」として親しまれている天神社は、令和4年に御造営800年という節目の年を迎えました。
天地創生の霊力をもつといわれる生成神・高皇産霊神(たかみむすびのかみ)を宮中の神殿にお祀りしています。
天神社では毎年1月15日前後に「古神符焼上祭」が境内にて執り行われます。
| 開催日時 | 毎年1月15日前後 午前10時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | しめ縄の持ち込みはご遠慮ください |
天神社「古神符焼上祭」
住所:〒635-0014 奈良県大和高田市三和町2-15
公式HP:https://takadatenjinsha.or.jp/
生蓮寺「とんど」|五條市
境内に咲く蓮が有名な生蓮寺は、嵯峨天皇の皇后の安産を祈願して地蔵尊を安置したのがはじまりと伝えられています。
弘法大師・空海が高野山開創の折に立ち寄り、彫り上げた小地蔵を本尊胎内に安置したことから、このあたり一帯の地名が寄足(よらせ)と呼ばれるようになりました。
晴れ乞い・雨乞い・子安安産の祈願所であることから、「雨晴れさん」と呼ばれ、毎年3月24日には、てるてる坊主をお焚き上げしています。
毎年1月14日に「とんど」が執り行われ、古い御札やお仏壇をお焚き上げしていただけます。
| 開催日時 | 毎年1月14日 午前9時〜午前10時 |
| 受付方法 | 納札所に納める |
| 注意点 | お問い合わせください |
生蓮寺「とんど」
住所:〒637-0071 奈良県五條市二見7-4-7
公式HP:https://www.ozizou.jp/
墨坂神社「神札焼上祭(とんど)」|宇陀市
墨坂神社は、大和のはやり病を鎮めるため、第十代崇神天皇により創建された日本最古の病気平癒の神を祀る神社です。
疫病の侵入などを防ぐ神々が御祭神であることから、厄除けや地鎮、方位除け、病気平癒、交通安全などのご利益があることで知られています。
毎年1月15日に執り行われる「神札焼上祭(とんど)」では、参拝者にぜんざいがふるまわれます。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前10時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
墨坂神社「神札焼上祭(とんど)」
住所:〒633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原703
公式HP:https://sumisaka-jinjya.jp/
転法輪寺「とんど供養」|御所市
真言宗醍醐派大本山・金剛山転法輪寺は、大阪と奈良の県境に位置する金剛山山頂に鎮座しています。
行基、鑑真、最澄が修行した場所と伝えられており、山伏行者の修行場として古くから栄えてきました。
ご本尊として、日本で誕生した五眼六臂(ごがんろっぴ:眼が5つ、腕が6本)の法起菩薩様が祀られています。
転法輪寺では毎年成人の日に「とんど供養」が執り行われ、古札やしめ縄などをお焚き上げします。個別にお祓いしてもらうことも可能です。
| 開催日時 | 毎年成人の日 午前10時 |
| 料金 | 古札供養料:志納 お祓い祈祷料:1千円 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
転法輪寺「とんど供養」
住所:〒639-2336 奈良県御所市大字高天472(金剛山山頂)
公式HP:https://www.katsuragi-syugen.or.jp/
千光寺「鳴川大とんど」|生駒郡平群町
生駒山の山麓の自然豊かな山里に位置する千光寺は、千光を発したといわれる千手観音像を役行者が祀ったことが名称の由来となったお寺です。
修行道場としても知られ、精神修養や荒行挑戦などの修行コースを体験できるとして知られています。
鳴川大とんどでは、高く組まれた櫓に点火し、古札や正月飾りをお焚き上げします。
立ち上った炎とともに火がはぜる音が響き渡り、荘厳な雰囲気の中進められます。
| 開催日時 | 毎年1月第2日曜日 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
千光寺「鳴川大とんど」
住所:〒636-0945 奈良県生駒郡平群町鳴川188
公式HP:https://motosanjyo-senkouji.com/
龍田大社「大とんど」|生駒郡三郷町
龍田大社は約2100年前、第十代崇神天皇が凶作や疫病の流行を危惧していたところ、ある日夢に大神様が現れ、御神託を授けられたことが開創のきっかけとなり、御神託通りにお社を造営したところ、作物が豊かに実り、疫病が退散したと言い伝えられています。
毎年1月15日に行われる「大とんど」は、同日に開催されるぼけ除け大祭とともに多くの参拝客で賑わいます。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前6時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | みかんや餅などの生もの・ビニール袋などの不燃物は不可 |
龍田大社「大とんど」
住所:〒636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南1-29−1
公式HP:https://tatsutataisha.jp/index.php
天河大辨財天社「とんど祭」|吉野郡天川村
日本三大弁天の宗家とされる天河大辨財天社。
ご本尊である辨財天は、川の流れを神格化した水の神であるのに加えて、音楽や芸能の神様として知られ、能楽の発祥に深く関わってきました。
能楽の創始者として名高い世阿弥が使用した能面や、太閤豊臣秀吉が奉納した唐織の装束などが保存されています。
毎年1月15日に「とんど祭」が行われ、前年にお祀りした御札や御守、しめ縄などを護摩壇でお焚き上げされます。
| 開催日時 | 毎年1月15日 午前6時 |
| 受付方法 | 納札所に納める |
| 注意点 | お問い合わせください |
天河大辨財天社「とんど祭」
住所:〒638-0321 奈良県吉野郡天川村坪内107
公式HP:https://www.tenkawa-jinja.or.jp/
玉置神社「古神札御焚き上げ祭」|吉野郡十津川村
霊峰玉置山の山頂近くに鎮座する世界遺産・玉置神社。古来より山岳修行の聖地として、多くの修験者が修行を重ねてきました。
境内には樹齢3000年と伝えられる神代杉をはじめ、樹齢1000年以上の大木が立ち並び、平成16年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産にも登録されています。
毎年1月28日に「古神札御焚き上げ祭」が執り行われ、忌火によって古いお札や縁起物などがお焚き上げされます。白煙がなびいていく様は壮観です。
| 開催日時 | 毎年1月28日 |
| 受付方法 | 納札所に納める |
| 注意点 | お問い合わせください |
玉置神社「古神札御焚き上げ祭」
住所:〒647-1582 奈良県吉野郡十津川村玉置川1
公式HP:https://tamakijinja.or.jp/
吉祥草寺「大とんど」|御所市
大和盆地を南に、金剛・葛城の山並を西に望む御所市茅原の地に鎮座している吉祥草寺。
不動明王をはじめとした五大尊が本尊として祀られているほか、薬師如来立像や地蔵菩薩立像などの木彫像を安置しています。
吉祥草寺のどんど焼きは「大とんど」という名称で毎年1月14日の夜に執り行われ、奈良県最大規模のとんどと言われています。
約1300年の歴史があり、奈良県指定無形民俗文化財にも指定されている伝統行事です。
高さ6m、直径3m、重さ700kgにもなる雄雌一対の松明に点火し、その年の平和を祈願します。
松明の火の勢いが弱まった後は、2基の松明の間を潜り抜ける「御渡り」を希望する参拝者で賑わいます。
| 開催日時 | 毎年1月14日 例年午後8時から午後9時 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | お問い合わせください |
吉祥草寺「大とんど」
住所:〒639-2241 奈良県御所市茅原279
奈良観光公式HP:https://en-chan.com/index.htm
春日大社「春日の大とんど」|奈良市
全国約3000社の春日神社の総本社である春日大社は、日本の繁栄と民の幸せを願って造営されました。約30万坪の広大な敷地を持ち、平成10年には世界遺産に登録されています。
毎年1月下旬に行われる「春日の大とんど」には県外からも多くの人が詰めかけ、境内の表参道にある飛火野に5mの大きな火炉を設置してお焚き上げが行われます。
ご神火は同日行われる若草山焼きの火種として使われます。
| 開催日時 | 毎年1月下旬 午後1時~午後6時頃 |
| 受付方法 | 持ち込み |
| 注意点 | 雨天時は翌日に順延 |
春日大社「春日の大とんど」
住所:〒630-8212 奈良県奈良市春日野町160
公式HP:https://www.kasugataisha.or.jp/
自宅から送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

どんど焼き開催情報をご紹介しましたが、「都合が合わず参加できない」「行きそびれてしまった」など、様々な事情で古いお守り・御札、正月飾りの処分にお困りの方もいらっしゃるかと思います。
そんな時には佐賀県鹿島市にある祐徳稲荷神社が行なっている郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」がおすすめです。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、品物を神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしてもらうことができます。
申し込み手順は以下の通り。
- 「お焚き上げキット」をサイトから購入
- キットが自宅に届く
- お焚き上げしたい品物を神社に送る
- 神社でご祈祷・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「お焚き上げ証明書」がメールで届く
送料は全て神社が負担してくれるので、自宅にいながら簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類やサイズに応じて様々なタイプがあり、小さめの正月飾りやお守り・御札をお焚き上げしたい方には、「レタータイプ」のキット(1,980円税込〜)がおすすめ。
大きめの正月飾りやしめ縄、ダルマなど、お焚き上げしたい物が複数ある場合には「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも送れるので、神棚や人形など、お焚き上げしたい物が他にもある場合は、一緒に入れて送りましょう。
多くのどんど焼き会場では、お守り・御札、正月飾り以外のものや、不燃物を受け付けてもらえない場合がほとんどですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは、不燃物も受け付けているので、分別せずにそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
自宅に古いお守り・御札、正月飾りが溜まっている方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
合わせて読みたい