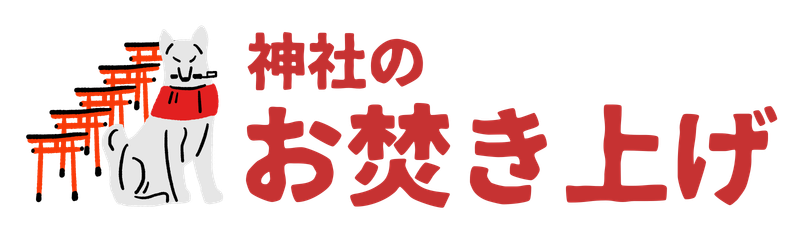人生で災難が降りかかりやすいとされる厄年。厄年は本厄と前厄・後厄の計3回ありますが、いずれも神社やお寺で厄払い(厄除け)を行うことで、穢れや邪気を祓い、災いを防ぐことができると言われています。
沖縄県内には、「縁切りスポット」として知られる波上宮をはじめ、琉球王国時代から信仰を集める首里観音堂、厄除けのご利益で有名な沖宮など、厄払い(厄除け)のご利益で広く親しまれている神社やお寺があります。
本記事では、沖縄県内で厄払い(厄除け)を検討している方に向けて、県内の最強スポットを詳しくご紹介します。
厄払いの御札・古いお守りを処分したい。
でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…
そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。
神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。
日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。
✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能
✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能
✅ クレジットカード、オンライン決済可
処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら
波上宮|那覇市若狭

波上宮は那覇港を望む断崖に鎮座する沖縄総鎮守で、伊弉冉尊・速玉男尊・事解男尊の熊野三神をお祀りします。
古来ニライカナイに祈る聖地と伝わり、厄除けや攘災招福の祈祷が広く行われてきました。
個人の厄祓いは社務所で当日受付ができ、祭典や挙式の時間帯を避けるため事前連絡が勧められます。
授与所では紅型守など沖縄らしいお守りに加え、魔除けの厄除神符「フーフダ」や台所を守る「竈神札(ヒヌカン)」も授与されるのが特徴です。
| 料金(個人) | 初穂料は公式未掲載のため社務所に要確認。 |
| 授与品 | 厄除神符「フーフダ」、竈神札(ヒヌカン)、波上宮神札、紅型守 など。 |
| 受付時間 | ご祈願:10:00〜15:30 授与:9:00〜16:30(社務所) ※正月期は変則。 |
| 予約/申込方法 | 社務所で当日受付可。 祭典・結婚式等の時間帯は受付不可のため、事前に社務所へ連絡・確認をおすすめします。 |
| 注意事項 | 年末年始は受付時間が特別設定・混雑あり。 境内駐車場は約20台で満車時は周辺有料Pを利用。 最新情報は公式で要確認。 |
波上宮(なみのうえぐう)
住所:沖縄県那覇市若狭1-25-11
公式HP:naminouegu.jp
沖縄県護国神社|那覇市奥武山町

沖縄県護国神社は那覇市奥武山町の奥武山公園内にあり、日清・日露戦争以降や沖縄戦で亡くなった沖縄出身および全国の戦没者、一般住民の御霊を祀る護国の社です。
昭和11年(1936年)に招魂社として創建され、昭和15年(1940年)に沖縄県護国神社と改称されました。
その歴史的背景から、地元の方々には「英霊への鎮魂」と「平穏な日常への祈り」を併せて捧げる祈願の場として親しまれており、初詣には約26万人の参拝者が訪れる沖縄県内有数の神社です。
厄除け・厄祓いの神様として知られており、人生の節目や災厄を払いたいと願う人々の参拝が絶えません。
祈祷は個人の厄年や前厄・後厄のほか、家族や将来の不安を清めたい方にも対応しています。
授与所では厄除けのお守り・お札を授与しており、持ち帰って生活や心に「清め」と「守り」をもたらすことができます。
| 料金(個人) | 初穂料は公式に明示されていないため、社務所で確認が必要。 |
| 授与品 | 厄除け・厄祓い向けのお守りやお札、祈願後に受け取れる授与品があり、生活に持ち帰って「清め」「守り」を得る品が含まれます。 |
| 受付時間 | ご祈願受付:9:30〜11:45 / 13:00〜16:00 (平日・土日祝とも) ※行事等により変更されることがあります。 |
| 予約/申込方法 | 個人の厄払い・厄除けの祈願は予約不要で、当日に社務所で申し込み可能です。 ただし、特定の祭典や団体祈願の時間帯には制限があるため事前確認が望ましいです。 |
| 注意事項 | 年始・初詣期間は祈願の受付時間や場所が通常と異なる場合があるため、事前に公式サイトや社務所で確認してください。 また、駐車場の一時利用制限や混雑状況にも注意が必要です。 |
沖縄県護国神社(おきなわけんごこくじんじゃ)
住所:沖縄県那覇市奥武山町44番地
公式HP:https://okinawa-gokoku.jp/
沖宮|那覇市奥武山町

沖宮は那覇市奥武山公園内に鎮座する琉球八社の一つで、1451年の創建とされ、琉球王国時代から航海安全や国家の安寧を願い、王府から厚く保護されてきました。
主祭神には天照大御神(天受久女龍宮王御神)をはじめ、天龍大御神、天久臣乙女王御神、熊野三神(伊弉册尊・速玉男尊・事解男尊)など複数の神々が祀られており、厄除けをはじめ家内安全、病気平癒、商売繁盛などの祈願が行われ、多くの参拝者が訪れます。
授与所では「御神塩」や厄除けの縁起物とされる「訶梨勒袋」(香袋)、各種「御守り」などが授与されており、持ち帰って日々の生活に清めと守護を取り入れることができるのが特色です。
| 料金(個人) | 初穂料(玉串料):5,000円〜 |
| 授与品 | 神前で清められた御神塩、お浄め用の香袋(訶梨勒袋など)、厄除け・攘災招福の御守り、各種授与符 |
| 受付時間 | 9:00〜16:00(社務所受付) |
| 予約/申込方法 | 当日、社殿に向かって左側の授与所にて直接申し込み可能。 ※祭典や結婚式等があるときは受付を休止する場合もあるので、事前の確認がおすすめ。 |
| 注意事項 | 祭典や行事時間帯は祈願を受けられない場合あり。 混雑時や初詣期間は待ち時間が長いことがあります。 駐車場は奥武山公園の公共Pを利用。 |
沖宮(おきのぐう)
住所:沖縄県那覇市奥武山町44番地(奥武山公園内)
公式HP:https://okinogu.or.jp/
普天間宮|宜野湾市普天間

普天間宮(普天滿宮/ふてんまぐう)は宜野湾市普天間に鎮座する琉球八社のひとつで、もともとは普天満の鍾乳洞(普天間洞穴)に琉球古神道の神々を祀ったことに起源を持ち、15世紀中頃に熊野権現を合祀したと伝わります。
その神秘的な洞窟と女神伝説により、「洞窟に籠った女神が災いを鎮めた」「神が人々に救いをもたらした」という言い伝えが厄払い・厄除けの信仰を強めてきました。
祈願後には「御神塩」「香袋」「厄除け御守」「記念の御札」など、清めや身代わり・守護の意味を持つ授与品が受け取れる点が特徴です。
| 料金(個人) | 公式には明示されていないため、事前確認が必要です。 |
| 授与品 | 御神塩、香袋またはお浄め袋、厄除け御守、記念の御札など。 (祈願後に授与される清め・守護の品) |
| 受付時間 | 祈願受付:10:00〜17:00(社務所/授与所) |
| 予約/申込方法 | 当日受付可(予約不要)。 ただし祭典・行事などで受付が中断されることがあるため、事前の確認がおすすめです。 |
| 注意事項 | 年末年始や初詣時期は混雑や特別対応があるため、受付時間や祈願の場所が変更される可能性があります。 洞窟拝観には別の受付や時間制限があるため、事前確認がおすすめです。 |
普天間宮(普天満宮/ふてんまぐう)
住所:沖縄県宜野湾市普天間1-27-10
公式HP:https://futenmagu.or.jp/
桃林寺|石垣市石垣

桃林寺(南海山桃林寺)は八重山列島で最も古い仏教寺院として1614年に創建され、臨済宗妙心寺派に属し本尊には観音菩薩(銅造観音像)が祀られています。
数度にわたる津波や戦火による壊滅的な被害からの復旧を繰り返してきた歴史があり、特に1771年の明和の大津波では仁王像や堂宇が流されたものの、後に打ち上げられて寺に戻った逸話から、“起死回生”や“再起”といった厄除け・復活のパワーを求める人々から信仰を集めています。
桃林寺では節分会・厄年対象の健康祈願の大般若祈祷会が行われ、参列者には厄除け祈祷の後、お守りや厄避けの御札、御朱印といった授与品が渡され、祈願後の「身を清め、再出発する」という気持ちを具体的に携えて帰ることができるのが特徴です。
境内は自由に参拝でき、御朱印や厄除けのお守りを求める多くの参拝者で賑わいます。
| 料金(個人) | 節分会・厄払いの大般若祈祷では冥加料として約3,000円/人 |
| 授与品 | 厄除けの御札、お守り、御朱印や記念の護符など。 節分会では七福神のお守りが添えられることもあります。 |
| 受付時間 | 通常の参拝は9:00~18:00 (季節・行事によって変動) 厄払い祈祷は節分会当日受付や寺務所にて確認が必要です。 |
| 予約/申込方法 | 節分会などの厄除け祈祷は当日境内の特設受付テントで申し込み。 通常の祈祷受付については事前に桃林寺へ問い合わせると安心です。 |
| 注意事項 | 節分会・初詣などの繁忙期は混雑・待ち時間あり。 住職不在や行事時間帯により御朱印・祈祷の受付が一時中断されることがあります。 |
桃林寺(とうりんじ)
住所:沖縄県石垣市字石垣285
公式HP:https://www.tourinji.net
沖縄成田山 福泉寺|中頭郡中城村伊舎堂

沖縄成田山 福泉寺(中城村伊舎堂)は、千葉・成田山新勝寺から分霊された不動明王を本尊とする真言宗のお寺で、中城山の中腹から太平洋を一望する高台に位置しています。
御本尊・不動明王へ捧げられる開運厄除・除災招福の御護摩祈祷が特に知られ、厄払い・災難除け・方位除けのご利益を求めて多くの参拝者が訪れます。
祈祷後には「護摩札」や「お守り」などの授与品が渡され、これを日常生活に持ち帰って厄を払ったり運を招いたりすることができます。
初詣や節分には特別な護摩祈祷が行われ、県内外からの参拝者で賑わう点も成田山福泉寺の厄除け祈願の魅力です。
| 料金(個人) | 初穂料・祈祷料:5,000円~ |
| 授与品 | 御護摩祈祷済みの御札、お不動さまのお守り、加持を受けた御加持印や御印紋(額印)など |
| 受付時間 | 開門時間:8:30〜17:00 通年 祈祷受付:基本的に日中随時(詳細は社務所に要確認) |
| 予約/申込方法 | 当日、境内または社務所にて御護摩祈祷の申し込み可。 事前連絡や予約も可能ですが、混雑時や節分・初詣などの特別行事時は受付体制が変わるため、事前確認をおすすめします。 |
| 注意事項 | 初詣や節分の護摩祈祷時は大変混雑し、祈祷受付や本堂の参拝に制限がかかることがあります。駐車場も混雑するため公共交通の利用が推奨されます。 山岳部分にあるため天候や工事などでアクセスや受付時間が変更されることがあります。 |
沖縄成田山 福泉寺(ふくせんじ)
住所:沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂617
公式HP:https://okinawa-naritasan.jp/
宮古神社|宮古島市平良西里

宮古神社(みやこじんじゃ)は1590年(天正18年)に創建された、沖縄本島から南西に位置する日本最南端の神社で、熊野三神と宮古島を治めた豊見親三神をお祀りしています。
沖縄本島・那覇の波上宮からの勧請による歴史と、宮古島の島々を守る信仰が融合した場所として、古くから「厄除け」「開運」「災難除け」の祈願所として知られています。
特に厄年や人生の転換期に訪れる人々が、宮古島特有の青い海と風景を背景に厄を祓い清め、新しい出発を祈る”厄除け祈祷”を受けることで心身をリセットしたいという思いを込めて参拝します。
御祈祷は社務所で随時受付され(受付時間9:00~17:00)、厄除けの御守や御札の授与があり、清めと守護を願うアイテムを持ち帰ることで日常生活での災難除けや運気の切り替えを期待できる点が人気です。
| 料金(個人) | 公式サイトでは具体的な金額の記載がないため事前に確認が必要です。 |
| 授与品 | 御朱印(書置きのみ、沖縄らしいブルーの紙にシーサーが描かれたデザイン、500円)や御守・御札など、神社で一般的に授与される守護・祈願の品。 |
| 受付時間 | ご祈願受付:9:00〜17:00(社務所) |
| 予約/申込方法 | 当日、社務所で直接申し込み可能。ただし祭典や神前結婚式の時間帯は祈願受付ができない場合があるため、事前に社務所への確認が推奨されます。 |
| 注意事項 | 初詣・例祭などの時期は混雑および祈願受付の制限が生じる場合があるため、時間や場所の変更に注意。 駐車場の混雑や待ち時間にも留意が必要です。 |
宮古神社(みやこじんじゃ)
住所:沖縄県宮古島市平良字西里5−1
公式HP:https://www.miyako-jinja.com/
厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。
お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。
厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。
お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。
「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。
最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。
- お焚き上げの依頼手順
- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する
- 自宅にキットが届く
- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る
- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる
- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)
送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。
「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。
御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。
いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。
多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。
古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜
家からお品を送るだけ
料金・手順はこちら